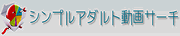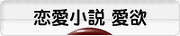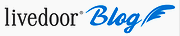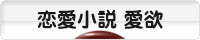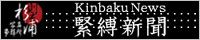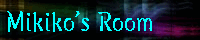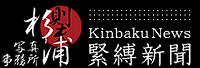↑「み」
16:14分の撮影。
もう、『浦佐駅』を過ぎてますね。
前方に見える川は、魚野川です。
信濃川の支流のひとつで、長岡市東川口(旧・北魚沼郡川口町)で信濃川に合流します。

↑「み」
16:22分。
もう『長岡駅』の手前です。
田植えからしばらく経ち、稲は順調に葉を伸ばしてます。

↑「み」
16:30分。
『長岡駅』を出ました。
変わり栄えのしない景色が、延々と続きます。
新潟平野の穀倉地帯が、いかに広いかわかります。

↑「み」
16:35分。
『燕三条駅』に着きました。
燕市と三条市の市境に位置する駅です。
所在地は北側の燕市・南側の三条市にまたがってます。

なお、登記上は駅長室のある三条市を所在地としています。
ちなみに、すぐ近くの北陸自動車道のインターチェンジは……。
『三条燕インターチェンジ』。

三条市の面積は、431.97km2。
人口は、9万7千人。
燕市の面積は、110.96km2
人口は、7万8千人。
人口は三条市が勝ってますが、人口密度なら燕市です。
仲の悪さは、『月曜から夜更かし』でも取りあげられました(くわしくは、こちら)。


↑「み」
16:41分。
『新潟駅』到着まで、あと8分。
まだ田園風景が続いてます。

↑「み」
『高崎駅』を出ると、景色は一気にひなびてきます。
まだ『上毛高原駅』の手前です。

↑「み」
『上毛高原駅』です。
雨まで降ってきました。
この後、上越新幹線は、『大清水トンネル』に入ります。

↑「み」
『大清水トンネル』を出ました。
撮影時刻を見たら、16:09分。
すでに、『越後湯沢駅』を過ぎてます。
これが冬だと、景色が激変してるんですけどね。
↓川端康成『雪国』の冒頭。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
この、「信号所」とは、いったい何でしょう?
調べてみると、現在の『土樽駅』のようです。
『雪国』が書かれたのは、昭和9(1934)年から昭和12(1937)年にかけてだそうです。
「国境の長いトンネル」である『清水トンネル』は、昭和6(1931)年の開通。
トンネルは単線です。
トンネルを出たところに、上下線の行き違いのための「信号所」がありました。
それが、『土樽信号場』です。
本来は駅ではありませんでしたが……。
昭和8(1933)年からは、スキーの季節中に限り、仮乗降場扱いで旅客営業を開始してたそうです。
上記『雪国』の冒頭は、↓に繋がります。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
向側の座席から娘が立って来て、島村の前のガラス窓を落した。雪の冷気が流れこんだ。娘は窓いっぱいに乗り出して、遠くへ叫ぶように、「駅長さあん、駅長さあん。」明りをさげてゆっくり雪を踏んで来た男は、襟巻で鼻の上まで包み、耳に帽子の毛皮を垂れていた。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
旅客営業をしてたので、「信号所」に駅長がいたわけです。
なお、『土樽信号所』が正式な駅になったのは、昭和16(1941)年1月10日のこと。
『土樽駅』の誕生です。
住所は、新潟県南魚沼郡湯沢町。
現在の『土樽駅』は無人駅ですので、「駅長さん」はいません。

↑現在の『土樽駅』。普通の駅ですね。
『清水トンネル』の反対側を出た駅は、『土合(どあい)駅』。

↑こちらは、かなり強烈。ホームから地上に出るまで、10分くらい階段を上らなくてはならないようです。
住所は、群馬県利根郡みなかみ町です。
まさしく、『清水トンネル』は、「国境の長いトンネル」だったわけです。
といっても、今の上越線の普通列車では、2駅間の所要時間は8分程度です。








![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)