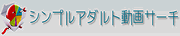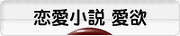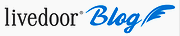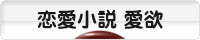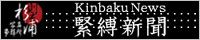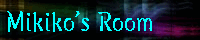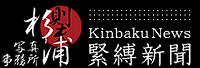婆「ほれ、行きますぞ」
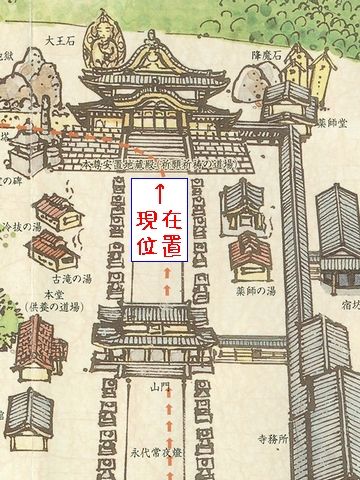
婆「目の前に見えるのが、『地蔵堂本殿』じゃ」

婆「ご本尊の地蔵菩薩がおわしまする」
み「見れるの?」
婆「ダメじゃ」

↑特別にご紹介。衣を着たお地蔵さまです。左に「掌善童子像(仏心を育てる)」、右に「掌悪童子像(煩悩を滅ぼす)」。
み「案外、ケチじゃの」
律「地蔵菩薩って、どういう仏様なんですか?」
婆「こういう質問を待っておった。
サンスクリット語では『クシティガルバ』と云う」

↑クシティガルバ像(チベット製)。日本の地蔵菩薩とは、だいぶ違います。
婆「“クシティ”は大地、“ガルバ”は胎内、子宮の意味で……。
意訳して『地蔵』としておる」
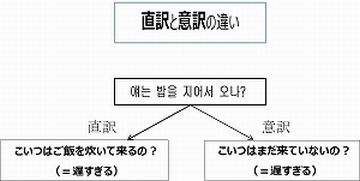
↑意訳とは、原文の一語一語にこだわらず、全体の意味をとって翻訳すること。
み「おー。
地蔵の“蔵”は、内臓の“蔵”だったのか!
ホルモン菩薩じゃな」

↑美味しいんですが、臭いがねー。噛み切れないし。
婆「罰あたりめ。
大地が、全ての命を育む力を蔵するように……。
苦悩する人々を、その無限の大慈悲の心で包みこみ、救うところから名付けられたとされておる」

↑興福寺『木造地蔵菩薩立像(重要文化財)』。
み「内臓で包むわけね。
ソーセージじゃな」

↑翌朝トイレで、これと同じものを見るんじゃないでしょうか。
婆「無視して進める。
日本における民間信仰では、道祖神としての性格を持つ。
道端におわしますじゃろ。
一般に、親しみを込めて“お地蔵さま”と呼ばれておる。

婆「これ以上知りたければ、自分で勉強しなされ」
み「ま、それは端折りましょう」

↑歌川広重『大はしあたけの夕立』の一部。雨に濡れないよう、着物の裾を折って帯に挟むことを“端折る”と云いました。
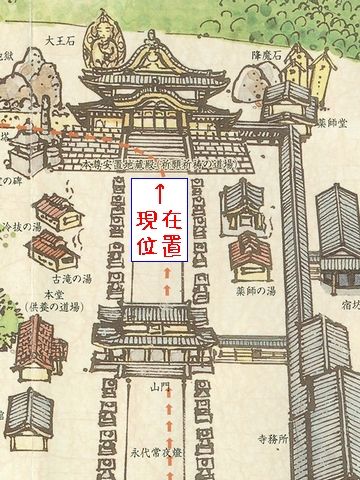
婆「目の前に見えるのが、『地蔵堂本殿』じゃ」

婆「ご本尊の地蔵菩薩がおわしまする」
み「見れるの?」
婆「ダメじゃ」

↑特別にご紹介。衣を着たお地蔵さまです。左に「掌善童子像(仏心を育てる)」、右に「掌悪童子像(煩悩を滅ぼす)」。
み「案外、ケチじゃの」
律「地蔵菩薩って、どういう仏様なんですか?」
婆「こういう質問を待っておった。
サンスクリット語では『クシティガルバ』と云う」

↑クシティガルバ像(チベット製)。日本の地蔵菩薩とは、だいぶ違います。
婆「“クシティ”は大地、“ガルバ”は胎内、子宮の意味で……。
意訳して『地蔵』としておる」
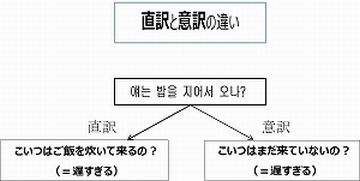
↑意訳とは、原文の一語一語にこだわらず、全体の意味をとって翻訳すること。
み「おー。
地蔵の“蔵”は、内臓の“蔵”だったのか!
ホルモン菩薩じゃな」

↑美味しいんですが、臭いがねー。噛み切れないし。
婆「罰あたりめ。
大地が、全ての命を育む力を蔵するように……。
苦悩する人々を、その無限の大慈悲の心で包みこみ、救うところから名付けられたとされておる」

↑興福寺『木造地蔵菩薩立像(重要文化財)』。
み「内臓で包むわけね。
ソーセージじゃな」

↑翌朝トイレで、これと同じものを見るんじゃないでしょうか。
婆「無視して進める。
日本における民間信仰では、道祖神としての性格を持つ。
道端におわしますじゃろ。
一般に、親しみを込めて“お地蔵さま”と呼ばれておる。

婆「これ以上知りたければ、自分で勉強しなされ」
み「ま、それは端折りましょう」

↑歌川広重『大はしあたけの夕立』の一部。雨に濡れないよう、着物の裾を折って帯に挟むことを“端折る”と云いました。
婆「ここに『男湯』と掲げてあれば男湯で……。
『女湯』とあれば、女湯じゃ」
み「いい加減な。
入ってる途中で掛け替えられたらマズいではないか」
婆「誰もいないときに、替えてるんじゃろ」
み「あの札は、ひょっとして……。
裏返すと『女湯』になるんじゃないのか?」

↑特命係のです。裏返すと赤字(外出)になります。
婆「何か、悪いことを考えておるじゃろ」
み「あれを『女湯』に裏返して入ったら……。
中に殿方がいても、言い訳が出来るではないか」
婆「確かに、そういう不届き者がおらんとも限らん。
裏返し方式ではないはずじゃ」
み「ほんまかー。
ちょっと見てくるかな」
律「いい加減にしなさい。
ほんと、子供より手間がかかるんだから」
婆「それじゃ、行きますぞ」
律「どうしたのよ」
み「今、あの窓に、人影が見えた」

み「裸の背中じゃった」
婆「湯小屋の中なんじゃから、裸で当然じゃろ」
み「窓の外を誰か通ったら、見られ放題ではないか。
露出狂か?」
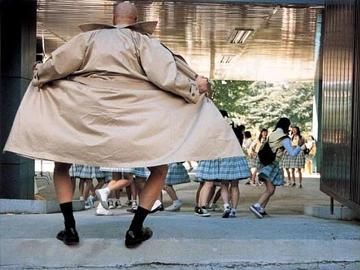
婆「恐山温泉では、窓を開けて入らなければならん」
み「なんでじゃー。
露出狂温泉ではないか」
婆「アホなことを言うでないわ。
硫黄泉じゃからじゃ。
入浴中は、換気しなければならんのじゃ」
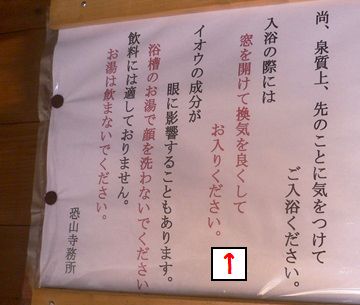
み「なるほど。
恐山で成仏してしまっては、洒落にならん。
しかし、堂々と露出できるとは……。
恐山は、露出狂の天国じゃな」
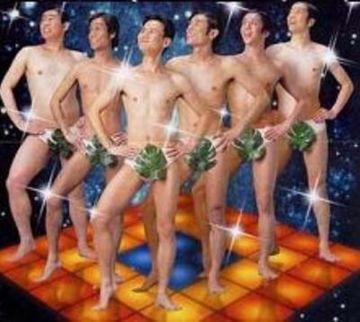
婆「後で、いくらでも入りなされ」
み「わたしが露出狂だと言いたいのか?」
婆「そうじゃないのか?」
み「見るのは好むが、見られるのは好まぬ」
婆「ただの痴漢ではないか」
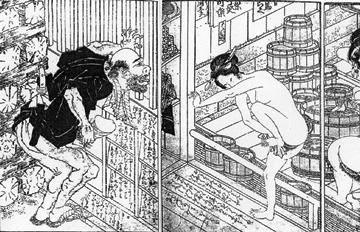
み「やかまし」
『女湯』とあれば、女湯じゃ」
み「いい加減な。
入ってる途中で掛け替えられたらマズいではないか」
婆「誰もいないときに、替えてるんじゃろ」
み「あの札は、ひょっとして……。
裏返すと『女湯』になるんじゃないのか?」

↑特命係のです。裏返すと赤字(外出)になります。
婆「何か、悪いことを考えておるじゃろ」
み「あれを『女湯』に裏返して入ったら……。
中に殿方がいても、言い訳が出来るではないか」
婆「確かに、そういう不届き者がおらんとも限らん。
裏返し方式ではないはずじゃ」
み「ほんまかー。
ちょっと見てくるかな」
律「いい加減にしなさい。
ほんと、子供より手間がかかるんだから」
婆「それじゃ、行きますぞ」
律「どうしたのよ」
み「今、あの窓に、人影が見えた」

み「裸の背中じゃった」
婆「湯小屋の中なんじゃから、裸で当然じゃろ」
み「窓の外を誰か通ったら、見られ放題ではないか。
露出狂か?」
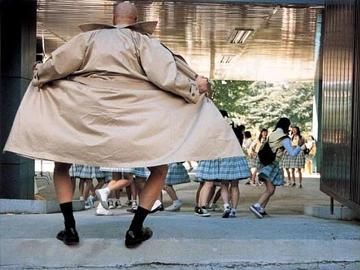
婆「恐山温泉では、窓を開けて入らなければならん」
み「なんでじゃー。
露出狂温泉ではないか」
婆「アホなことを言うでないわ。
硫黄泉じゃからじゃ。
入浴中は、換気しなければならんのじゃ」
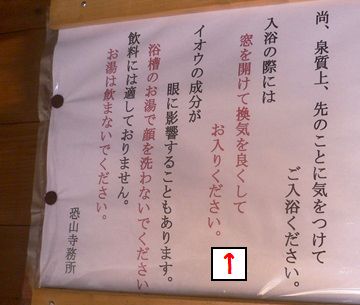
み「なるほど。
恐山で成仏してしまっては、洒落にならん。
しかし、堂々と露出できるとは……。
恐山は、露出狂の天国じゃな」
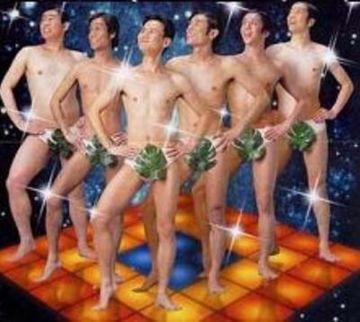
婆「後で、いくらでも入りなされ」
み「わたしが露出狂だと言いたいのか?」
婆「そうじゃないのか?」
み「見るのは好むが、見られるのは好まぬ」
婆「ただの痴漢ではないか」
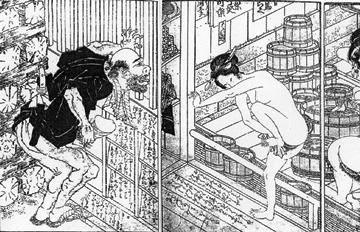
み「やかまし」








![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)