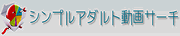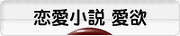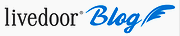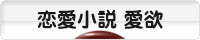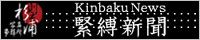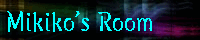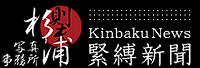2022.7.12(火)
てなわけで、棚からぼた餅みたいなかたちで……。
この「日月」日程の利点に気づけたわけです。
でも、月曜に帰って、翌日出勤だと、ちょっと大変。
月曜日の帰りは、気分的にもよろしくないと思います。
ということで……。
月火と、有給休暇を取りました。
2019年のときもそうでした。
うちの会社には、リフレッシュ休暇の取得をうながす制度があります。
土日に繋げて、4連休を取ることが奨励されてるんです。
もちろん、有給休暇を使うわけですが。
なので、「リフレッシュ休暇」という名目で申請を出せば……。
却下されることはまずありません。
火曜が休めるとなれば、月曜の帰りも気分が沈みませんね。
旅は、最後まで楽しみたいですから。
それでは、再び仕切り直し。
2022(令和4)年。
初夏。
日曜日。
嬉しかったのは、お天気に恵まれたこと。
「単独旅行」は、雨に祟られることが多いんですよね。
梅雨時に行ってたので、当たり前なんですが。
3月が会社の決算月で、5月が申告月なので……。
3月末から5月一杯は忙しいんです。
でも今年は、何とか仕事をやりくりして……。
梅雨入り前の旅程を組みました。
日ごろの精進のおかげか……。
天気予報は、2日間とも降水確率ゼロ。
折りたたみ傘も持たずに行けました。
さて。
初日。
家を出たのは、8時半前。
あ、日曜日でいいことが、もうひとつあります。
駅も電車も空いてること。
平日に行ってたときは、通勤客がたくさんいました。
その電車に、大きなリュックを背負った行楽スタイルで乗りこむのは……。
ちょっと気恥ずかしかったです。
家からの描写はちょっと端折って……。
まずは、この旅の起点の駅に降り立ちます。

「新津駅」です。
今日は、JR東日本の磐越西線で会津若松に向かいます。
磐越西線は、福島県の「郡山駅」が起点。
「会津若松駅」を経由して、新潟県の「新津駅」が終点になります。
「郡山駅」から「会津若松駅」を経て……。
ラーメンで有名な福島県の「喜多方駅」までが電化されてます。
「喜多方駅」から「新津駅」までは、非電化。
なお、「会津若松駅」から「喜多方駅」間には……。
電車による定期列車は運行されてないそうです。
電化が整備されるのも、起点から順番なんですかね。
なお、終点は「新津駅」ですが……。
多くの列車が、「新潟駅」まで乗り入れてます。
なのでわたしは、日常的にディーゼル車を見てます。
電車とは、ぜんぜん音が違うんですよ。
新しい車両は、エンジン音がいっそう喧しくなった気がします。
なんでですかね?
さて、「新津駅」。
磐越西線のほか、信越本線と羽越本線が乗り入れてます。
信越本線は、群馬県や長野県も通ってますが……。
新潟県内では、上越市の「直江津駅」から新潟市の「新潟駅」を結んでます。
羽越本線は、「新津駅」が起点で、秋田県の「秋田駅」が終点。
「新津駅」は、この3路線が乗り入れる鉄道の要衝なのです。
うち、2つの路線では、「起点(羽越本線)」と「終点(磐越西線)」ですからね。
こんなことから、新津は……。
機関区、工場、操車場を有する「鉄道の街」として栄えました。
昔は、新津市という独立した自治体でした。
人口は、7万人弱だったようです。
今は、新潟市秋葉区の中心地となってます。
「新津駅」は、2003(平成15)年に改築されてます。
それに伴い、駅前の広場も整備されたようです。
かつての「鉄道の街」を彷彿とさせる展示物もありました。
出発まで少し時間があるので、駅の回りを見てみましょう。
↓さっそくありました。
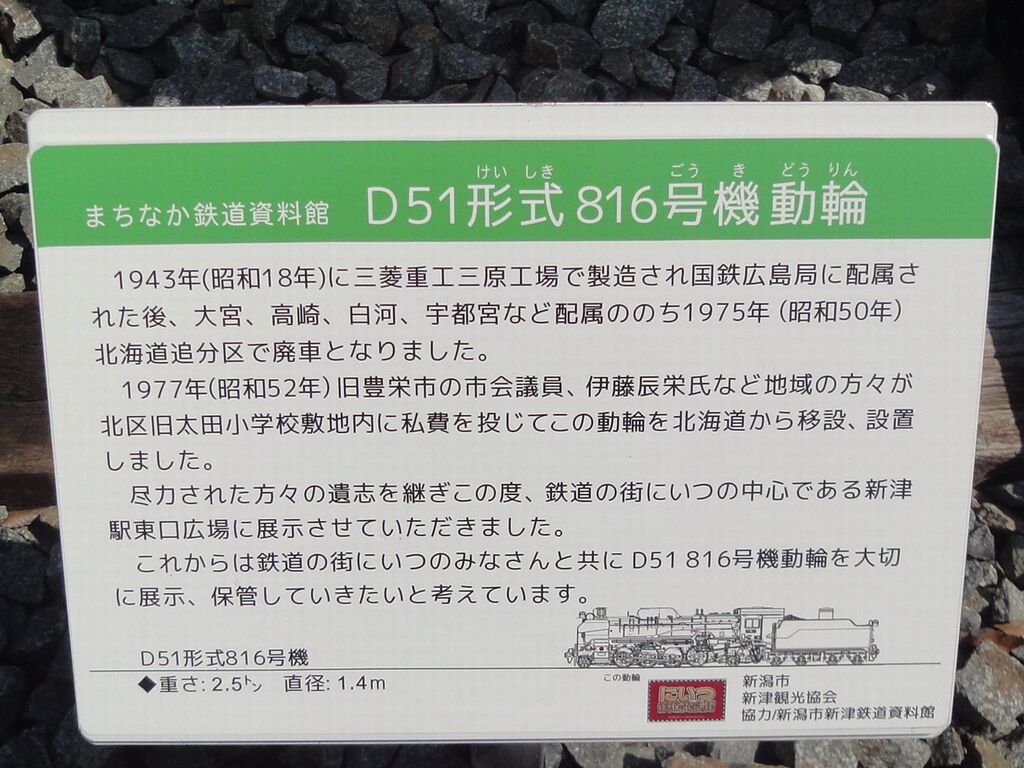
↓こちらが全容です。

うーむ。
比べるものが周りにないので、大きさがわかりませんね。
説明板には、直径1.4メートルと書いてあります。
軽自動車の横幅くらいです。
まぁ、大きいことは確かです。
↓駅から続く商店街。

切ないほど寂れてます。
かつては両側に、アーケードが連なってたそうです。
老朽化により、撤去されました。
建て替える力は、もう商店街には残ってなかったんです。
この「日月」日程の利点に気づけたわけです。
でも、月曜に帰って、翌日出勤だと、ちょっと大変。
月曜日の帰りは、気分的にもよろしくないと思います。
ということで……。
月火と、有給休暇を取りました。
2019年のときもそうでした。
うちの会社には、リフレッシュ休暇の取得をうながす制度があります。
土日に繋げて、4連休を取ることが奨励されてるんです。
もちろん、有給休暇を使うわけですが。
なので、「リフレッシュ休暇」という名目で申請を出せば……。
却下されることはまずありません。
火曜が休めるとなれば、月曜の帰りも気分が沈みませんね。
旅は、最後まで楽しみたいですから。
それでは、再び仕切り直し。
2022(令和4)年。
初夏。
日曜日。
嬉しかったのは、お天気に恵まれたこと。
「単独旅行」は、雨に祟られることが多いんですよね。
梅雨時に行ってたので、当たり前なんですが。
3月が会社の決算月で、5月が申告月なので……。
3月末から5月一杯は忙しいんです。
でも今年は、何とか仕事をやりくりして……。
梅雨入り前の旅程を組みました。
日ごろの精進のおかげか……。
天気予報は、2日間とも降水確率ゼロ。
折りたたみ傘も持たずに行けました。
さて。
初日。
家を出たのは、8時半前。
あ、日曜日でいいことが、もうひとつあります。
駅も電車も空いてること。
平日に行ってたときは、通勤客がたくさんいました。
その電車に、大きなリュックを背負った行楽スタイルで乗りこむのは……。
ちょっと気恥ずかしかったです。
家からの描写はちょっと端折って……。
まずは、この旅の起点の駅に降り立ちます。

「新津駅」です。
今日は、JR東日本の磐越西線で会津若松に向かいます。
磐越西線は、福島県の「郡山駅」が起点。
「会津若松駅」を経由して、新潟県の「新津駅」が終点になります。
「郡山駅」から「会津若松駅」を経て……。
ラーメンで有名な福島県の「喜多方駅」までが電化されてます。
「喜多方駅」から「新津駅」までは、非電化。
なお、「会津若松駅」から「喜多方駅」間には……。
電車による定期列車は運行されてないそうです。
電化が整備されるのも、起点から順番なんですかね。
なお、終点は「新津駅」ですが……。
多くの列車が、「新潟駅」まで乗り入れてます。
なのでわたしは、日常的にディーゼル車を見てます。
電車とは、ぜんぜん音が違うんですよ。
新しい車両は、エンジン音がいっそう喧しくなった気がします。
なんでですかね?
さて、「新津駅」。
磐越西線のほか、信越本線と羽越本線が乗り入れてます。
信越本線は、群馬県や長野県も通ってますが……。
新潟県内では、上越市の「直江津駅」から新潟市の「新潟駅」を結んでます。
羽越本線は、「新津駅」が起点で、秋田県の「秋田駅」が終点。
「新津駅」は、この3路線が乗り入れる鉄道の要衝なのです。
うち、2つの路線では、「起点(羽越本線)」と「終点(磐越西線)」ですからね。
こんなことから、新津は……。
機関区、工場、操車場を有する「鉄道の街」として栄えました。
昔は、新津市という独立した自治体でした。
人口は、7万人弱だったようです。
今は、新潟市秋葉区の中心地となってます。
「新津駅」は、2003(平成15)年に改築されてます。
それに伴い、駅前の広場も整備されたようです。
かつての「鉄道の街」を彷彿とさせる展示物もありました。
出発まで少し時間があるので、駅の回りを見てみましょう。
↓さっそくありました。
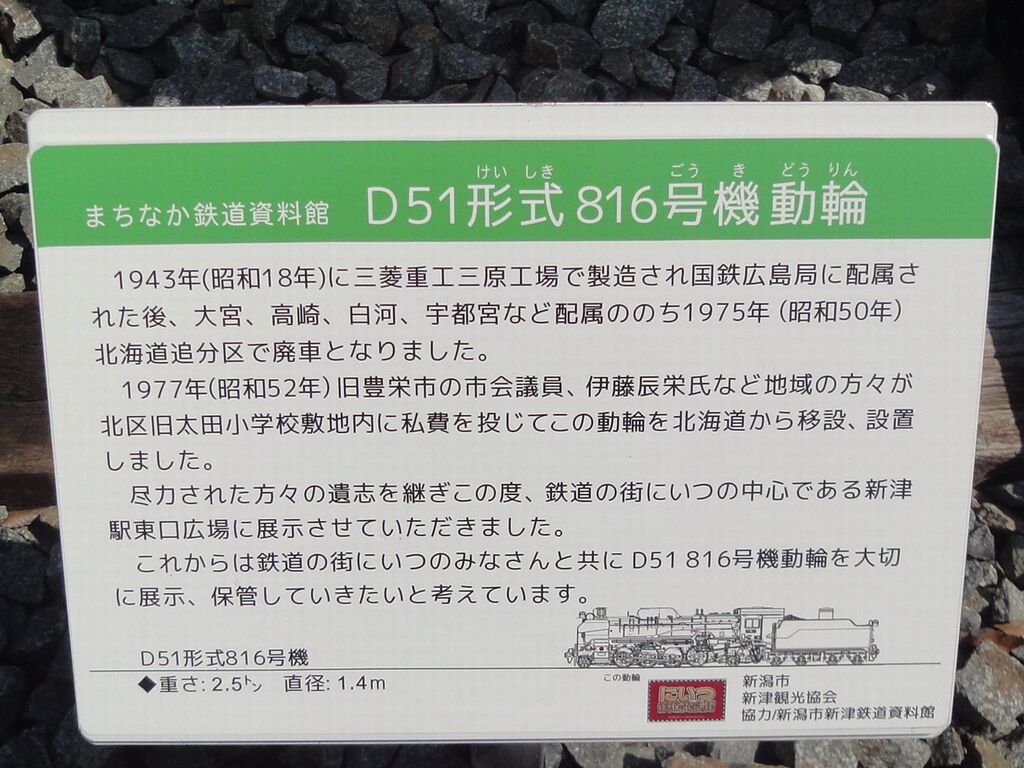
↓こちらが全容です。

うーむ。
比べるものが周りにないので、大きさがわかりませんね。
説明板には、直径1.4メートルと書いてあります。
軽自動車の横幅くらいです。
まぁ、大きいことは確かです。
↓駅から続く商店街。

切ないほど寂れてます。
かつては両側に、アーケードが連なってたそうです。
老朽化により、撤去されました。
建て替える力は、もう商店街には残ってなかったんです。
コメント一覧
-
––––––
1. Mikiko- 2022/07/12 06:03
-
 鉄道の要衝、新津
鉄道の要衝、新津
もう、だいぶ前のことですが……。
『新津鉄道資料館(https://www.ncnrm.com/)』に行ったことがあります。
自転車で行きました。
夏の終わりでしたね。
自転車で行くには、かなりの距離があります。
車もあったのに、なんで自転車にしたのか……。
動機は思い出せません。
終わってしまう夏を、最後にかみしめたかったのかも知れません。
当時は、『Mikiko's Room』もやってなくて、ヒマでしたし。
資料館の展示内容については……。
正直、さほどのものではありませんでした。
でも、わたしが行った後、リニューアルされてるんですよ。
またいつか、行ってみたいと思ってます。
今度は車で。
さて、新津駅には、名物があります。
三色団子。
大正時代から売られてるようです。
折りに入ってます。
一見、お団子には思えません。
串も団子も見えませんから。
折りの縁ギリギリまで、三色の餡で覆われてるんです。
串と団子は、その下に埋もれてます。
餡は、ごま餡、白餡、こし餡。
なので、華やかな色彩ではありません。
灰色、白、茶色、と云った感じ。
わたしも、たぶん食べたことあります。
なんとなく、味の記憶がありますから。
甘すぎなくて食べやすかったと思います。
こちら(https://colocal.jp/news/31484.html)のページに、詳しいレポートが載ってました。








![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)