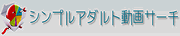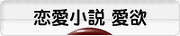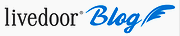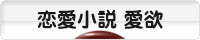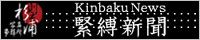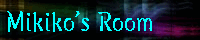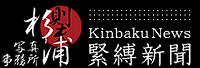2020.12.4(金)
「立派な変態だな。
そんなに違うのか、味」
「ぜんぜん別の味ってことはないわよ。
精液には変わりがないんだから。
でも、バリエーションがあることは確かね。
一般的には、苦みかな。
塩っぱい人も甘い人もいた。
体調によっても変わるみたいだし。
でも、昭夫ほど甘いのは初めてだった。
言われなかった?」
「誰に?」
「奥さんとか、ほかの女性とか」
「妻は、バージンだったからな。
精液見たのも、おれのが初めてだったはずだ。
ほかの女性ったって、ほとんどが風俗嬢だし。
顔射は、オプション料金がかかるからね」
「味見してもらったことはない?」
「ないね」
「あの子は?」
「あの子って、誰だよ」
「前のアパートの隣の子よ。
女工さん」
「女工って、いつの時代の話だ」
「じゃ、女子工員?
なんだか、銀行員と区別がつかないじゃない。
それにあの子は、いかにも女工って感じだったわ。
不幸が背中に張りついてる感じ」
「ちゃんと結婚したじゃないか。
イケメンの彼氏と。
おれたちが仲人みたいなもんだったし」
「そうね。
仲良く暮らしてるかしら」
「そうなんじゃないのか。
便りのないのはなんとやらだ。
こっちの住所も知らせてあるし、携帯番号はそのままだし。
何かあったら、仲人に相談するものだろう」
「ほんとに会ってないの?」
「会ってないって。
なんでだよ」
「知らないとでも思ってるわけ?」
「何を」
「彼女と、やったでしょ」
「……」
「ふふ。
嘘が下手なの自覚してるから、黙っちゃうのよね」
「おまえだって、あっただろ。
彼氏と」
「そうね。
だから、お互いさまよ。
そうそう。
あの彼氏のは、ほとんど味がしなかった」
「そういうことまでしてたわけ」
「逆よ。
最初のとき。
猛ってたから、口で処理してやったの」
「いちおう、操を立てたってこと」
「そうよ。
でもその後は……」
「本番もやるようになった」
「昭夫だってそうでしょ」
そんなに違うのか、味」
「ぜんぜん別の味ってことはないわよ。
精液には変わりがないんだから。
でも、バリエーションがあることは確かね。
一般的には、苦みかな。
塩っぱい人も甘い人もいた。
体調によっても変わるみたいだし。
でも、昭夫ほど甘いのは初めてだった。
言われなかった?」
「誰に?」
「奥さんとか、ほかの女性とか」
「妻は、バージンだったからな。
精液見たのも、おれのが初めてだったはずだ。
ほかの女性ったって、ほとんどが風俗嬢だし。
顔射は、オプション料金がかかるからね」
「味見してもらったことはない?」
「ないね」
「あの子は?」
「あの子って、誰だよ」
「前のアパートの隣の子よ。
女工さん」
「女工って、いつの時代の話だ」
「じゃ、女子工員?
なんだか、銀行員と区別がつかないじゃない。
それにあの子は、いかにも女工って感じだったわ。
不幸が背中に張りついてる感じ」
「ちゃんと結婚したじゃないか。
イケメンの彼氏と。
おれたちが仲人みたいなもんだったし」
「そうね。
仲良く暮らしてるかしら」
「そうなんじゃないのか。
便りのないのはなんとやらだ。
こっちの住所も知らせてあるし、携帯番号はそのままだし。
何かあったら、仲人に相談するものだろう」
「ほんとに会ってないの?」
「会ってないって。
なんでだよ」
「知らないとでも思ってるわけ?」
「何を」
「彼女と、やったでしょ」
「……」
「ふふ。
嘘が下手なの自覚してるから、黙っちゃうのよね」
「おまえだって、あっただろ。
彼氏と」
「そうね。
だから、お互いさまよ。
そうそう。
あの彼氏のは、ほとんど味がしなかった」
「そういうことまでしてたわけ」
「逆よ。
最初のとき。
猛ってたから、口で処理してやったの」
「いちおう、操を立てたってこと」
「そうよ。
でもその後は……」
「本番もやるようになった」
「昭夫だってそうでしょ」
コメント一覧
-
––––––
1. Mikiko- 2020/12/04 06:00
-

 今日は何の日
今日は何の日
12月4日は、『血清療法の日』。
1890(明治23)年12月4日(今から130年前)……。
北里柴三郎とエミール・ベーリングが、連名で、破傷風とジフテリアの血清療法の発見を発表しました。
血清療法とは、菌体を少量ずつ動物に注射しながら血清中に抗体を生み出し……。
その抗体のある血清を患者に注射することで、体内に入った毒素を中和して無力化する治療法です。
日本の医学者で細菌学者の北里柴三郎(きたざと しばさぶろう/1853~1931)は、「日本の細菌学の父」として知られ……。
感染症ペストの病原体であるペスト菌の発見や、破傷風の治療法を開発するなど、感染症医学の発展に貢献しました。
私立伝染病研究所(現:東京大学医科学研究所)の創立者、初代所長、土筆ヶ岡養生園(現:東京大学医科学研究所附属病院)の創立者、運営者、私立北里研究所、北里研究所病院(現:学校法人北里研究所)の創立者、初代所長、慶應義塾大学医学科(現:慶應義塾大学医学部)の創立者、初代医学科長、日本医師会の創立者、初代会長でもあります。
上記の記述は、こちら(https://zatsuneta.com/archives/112042.html)のページから転載させていただきました。
続きは次のコメントで。
-
––––––
2. Mikiko- 2020/12/04 06:00
-

 今日は何の日(つづき)
今日は何の日(つづき)
さらに同じページから、引用を続けさせていただきます。
ドイツの医学者で実業家のエミール・ベーリング(Emil Behring、1854~1917)は……。
「ジフテリアに対する血清療法の研究」で、1901(明治34)年の第1回ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
北里は破傷風を、ベーリングはジフテリアを研究してました。
特にジフテリアの場合は、エミール・ルーのジフテリア毒素の発見もあって、血清療法の進展にとって画期的なものとなり……。
後の、第1回ノーベル賞受賞に繋がりました。
ただし、ベーリングのジフテリア血清療法は、北里の破傷風血清療法を基にしたものであり……。
ベーリング本人も、北里あっての受賞であることを認めてます。
また、北里は受賞はできませんでしたが、第1回ノーベル生理学・医学賞の最終候補者(15名のうちの1人)に名前が挙がっていました。
ベーリングは、単独名でジフテリアについての論文を別に発表していたことなどが、その受賞に繋がったとされてます。
以上、引用終わり。
日本人のノーベル賞第1号は、1949(昭和24)年の湯川秀樹。
もし、北里が第1回のノーベル賞を受賞してたら……。
その48年も前だったということです。
続きはさらに次のコメントで。
-
––––––
3. Mikiko- 2020/12/04 06:01
-

 今日は何の日(つづきのつづき)
今日は何の日(つづきのつづき)
↑のさまざまな“初代”の中に、北里大学がないのが不思議でした。
調べて見たら、それもそのはず、北里大学の創立は、1962(昭和37)年でした。
柴三郎の死後、31年経ってからです。
しかし、その源は、↑にある「北里研究所」だそうです。
ということで、北里柴三郎は……。
北里大学の「学祖」となってるようです。
しかしねー。
今さらですが、お医者さんにとっては大変な時代になりました。
コロナ患者を治療してるお医者さんの中には……。
病院駐車場の車で寝泊まりしてた方もいたそうです。
家に帰って家族にうつしたり、近隣住民の目が心配で、家に帰れなかったわけです。
ほんとに、この国に失望しかけるほど情けないことでした。
そのコロナ、ここに来て、またヒドくなってますね。
そのくせ政府は、GoToトラベルの中止にも及び腰で……。
学校の休校など、まったく考えないというスタンスです。
今年の春の、街が死んだようになった光景が、よほど堪えたのでしょう。
実際、経済が止まってしまえば、税収が絶たれます。
医療を支えたり、さまざまな助成事業を行う予算が、消えてなくなってしまうわけです。
でも、はなはだ不謹慎な話で申し訳ないのですが……。
わたしは今、あの穏やかで静かだった春が、妙に懐かしいです。
電車に座って通えたんですよ。
ボックスシートにひとりだけ腰掛け……。
春の日を浴びてると、うとうとしてきたものです。
ほんとに今思えば、おとぎ話のような日々でした。
-
––––––
4. 手羽崎 鶏造- 2020/12/05 10:12
-
「女工愛し」という有名な
書物がありましたな。
ワタシはもっぱら「人妻愛し」
ですねん。
-
––––––
5. Mikiko- 2020/12/05 11:46
-
 女工哀史
女工哀史
富岡製糸場では、工女と呼ばれてたようです。
技術を極めた一等工女は、赤いタスキと高草履を許され……。
給金も破格だったそうです。








![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)