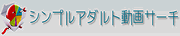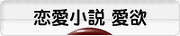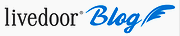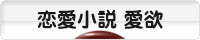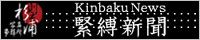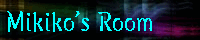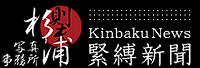2018.11.14(水)
しかし、銭湯というのも、重要な日本文化のひとつです。
区じゃ難しいと思いますので……。
都の直営で、昔ながらの銭湯を残すべきじゃないでしょうか。
でも、番台に座る人の人選が、ちと問題ですね。
都の職員ですか?
↓もうテレビが入ってる時代の茶の間ですね。

↑「み」
団らんが終わったら、ここに布団を敷いて寝たんだと思いますが……。
布団を入れる押し入れがないですね。
あ、ひょっとしたら、こちら側の開口部が押し入れスペースなんですかね?
左に下駄があるところは、玄関ではなく、勝手口でしょう。

↑まさしくこれです。男性は、『三河屋』さんの御用聞きですね。
しかし、框がこんなに低かったんでしょうか?
縁の下がないことになります。
↓まさしく、勝手口の隣には、お勝手(台所)があります。

↑「み」
↓電気釜とガス台、あとは流し。

↑「み」
電気釜は、『東芝』が1955(昭和30)年に発売を開始したものだそうです。

↑輸出用ポスター。まさか、輸出もしてたとは思いませんでした。どういう人が買ったんでしょう?
お米を研いで、分量の水を入れてセットし……。
電気釜の中央下部に見えるスイッチを押すと、ご飯が炊けます。
炊き上がると、ガチョンと音を立ててスイッチが切れる仕組み。
トースターみたいですね。
↑トースターに驚く猫。
今どきの炊飯器のように、タイマーもなければ保温機能もないそうですが……。
それで十分だと思います。
わたしが東京に住んでたころ使ってた炊飯器も、この機能だけだったと思います。
わたしはお冷やご飯が大好きなので、保温されない不便はまったく感じませんでした。
いろいろ付いてれば、それだけ故障する原因も多くなるわけですし。

↑現代の主流、IH(電磁式)炊飯器。この製品は、炊飯器部分を外してIHクッキングヒーターとしても使えるそうです。壊れたとき、何にも料理出来なくなりますね。
ガス台と流しは、職人さんがその場でトタン板を曲げて作ったようです。
昔の職人さんは、こうした「現場合わせ」が出来ました。
今は、キッチンユニットを搬入するだけです。
洗面器はホーロー、食器洗いは亀の子束子ですね。

区じゃ難しいと思いますので……。
都の直営で、昔ながらの銭湯を残すべきじゃないでしょうか。
でも、番台に座る人の人選が、ちと問題ですね。
都の職員ですか?
↓もうテレビが入ってる時代の茶の間ですね。

↑「み」
団らんが終わったら、ここに布団を敷いて寝たんだと思いますが……。
布団を入れる押し入れがないですね。
あ、ひょっとしたら、こちら側の開口部が押し入れスペースなんですかね?
左に下駄があるところは、玄関ではなく、勝手口でしょう。

↑まさしくこれです。男性は、『三河屋』さんの御用聞きですね。
しかし、框がこんなに低かったんでしょうか?
縁の下がないことになります。
↓まさしく、勝手口の隣には、お勝手(台所)があります。

↑「み」
↓電気釜とガス台、あとは流し。

↑「み」
電気釜は、『東芝』が1955(昭和30)年に発売を開始したものだそうです。

↑輸出用ポスター。まさか、輸出もしてたとは思いませんでした。どういう人が買ったんでしょう?
お米を研いで、分量の水を入れてセットし……。
電気釜の中央下部に見えるスイッチを押すと、ご飯が炊けます。
炊き上がると、ガチョンと音を立ててスイッチが切れる仕組み。
トースターみたいですね。
↑トースターに驚く猫。
今どきの炊飯器のように、タイマーもなければ保温機能もないそうですが……。
それで十分だと思います。
わたしが東京に住んでたころ使ってた炊飯器も、この機能だけだったと思います。
わたしはお冷やご飯が大好きなので、保温されない不便はまったく感じませんでした。
いろいろ付いてれば、それだけ故障する原因も多くなるわけですし。

↑現代の主流、IH(電磁式)炊飯器。この製品は、炊飯器部分を外してIHクッキングヒーターとしても使えるそうです。壊れたとき、何にも料理出来なくなりますね。
ガス台と流しは、職人さんがその場でトタン板を曲げて作ったようです。
昔の職人さんは、こうした「現場合わせ」が出来ました。
今は、キッチンユニットを搬入するだけです。
洗面器はホーロー、食器洗いは亀の子束子ですね。

コメント一覧
-
––––––
1. Mikiko- 2018/11/14 07:20
-
 三河屋
三河屋
「ちわー、三河屋です」
昔のホームコメディなどでは、必ず登場した職業のようです。
『三河屋』は、もちろん屋号ですが……。
特定の食材を扱う小売店の俗称となってます。
一般的に、酒、味噌、醤油、酢など……。
醸造された食品がその取扱品目。
もちろん、これらの食品だけではなく……。
ジュースや牛乳などの飲料、調味料、乾物、缶詰なども置いてあります。
1960年代までは……。
味噌や醤油といった食品では、店内に樽が置かれていて、その都度量り売りがされてたそうです。
その昔は、お酒もそうでしたよね。
浪人が貧乏徳利を下げて買いに行ったわけです。
醸造業の盛んな三河の出身者が多かったため……。
『三河屋』の看板を掲げる店が多かったそうなんです。
ところで、三河ってどこなんでしょう?
愛知県だと云うことはぼんやりわかってました。
でも、名古屋は、尾張名古屋ですよね。
それでは、三河はどこ?
どうやら愛知県は縦に3つに分割でき……。
一番左が、尾張。
真ん中が、西三河。
一番右が、東三河。
↓だそうです。
https://matome.naver.jp/odai/2143469733163888501
豊田市、岡崎市などが、西三河。
豊橋市、豊川市などが、東三河。
しかしやっぱり、“豊"が好きなんですね。
続きは次のコメントで。
-
––––––
2. Mikiko- 2018/11/14 07:21
-
 三河屋(つづき)
三河屋(つづき)
さて。
現在、この『三河屋』さん。
ほとんど無くなってしまったんじゃないでしょうか。
ま、酒屋さんとしては残ってるのでしょうが。
あと、今、少なくなったお店にお米屋さんがありますね。
これは、『三河屋』よりも更に少なくなってる気がします。
両者の特徴は、扱う商品が重いということ。
昔は、マイカーが普及してませんでした。
お米は大袋でしか売ってません。
お酒も瓶です。
米や酒を自転車で買って帰るのは、はなはだ困難。
運んでもらうしかないわけです。
特に、団地などでは、エレベーターもありませんからね。
部屋まで運んでもらえるメリットは、ものすごく大きかったはずです。
しかし、包装も小袋化され、マイカーも普及するにつれ……。
自分で持ち帰れるようになりました。
スーパーで特売などをやってれば、そっちの方がお得感がありますし。
というわけで、『三河屋』さんや米屋さんが、減っていったわけです。
もちろん、お客だけの問題じゃないでしょう。
配達は重労働です。
歳を取ったら出来ません。
若いうちに腰を痛めた人も多かったんじゃないですか。
子供にはとても継がせられない。
しかし、最近は、また需要が出て来てるはずです。
免許を返納したお年寄りや、近くに店舗が無くなった地域などがありますから。
いわゆる、買い物弱者という人たち。
でも……。
成り手は見つからないと思います。
需要はあるけど、それに応じられる人がいない。
やっぱり、役所の直営でやるしかないんじゃないですか。
これからは、民間に委託するのではなく……。
再び、役所が直営を行う時代に戻るべきじゃないでしょうか。
昔は、道路工事なんかも、役所の直営部隊がやってたそうです。
-
––––––
3. 手羽崎 鶏造- 2018/11/14 23:06
-
米屋、酒屋の衰退は、「規制緩和」による
政策的な原因です。
かつては販売の免許証のようなものが
必要でした。
大手スーパーや大手コンビ二チェーンは
そのカベを除去しようと、規制緩和を政権に
求めた結果といえます。
その結果、地方にシャッター商店街が
増えてしまいましたね。
-
––––––
4. Mikiko- 2018/11/15 07:17
-
 確かに……
確かに……
昔は、スーパーでお酒は売られてなかったように思います。
今では、郊外のスーパーで何でも揃ってしまいます(わたしも利用してますが)。
スーパーは客寄せのために、大々的に新聞広告を入れて……。
特定の商品を、原価割れで売ったりします。
特定の商品だけを扱う小売店には、対抗する手段がありません。








![[官能小説] 熟女の園](https://livedoor.blogimg.jp/mikikosroom2008/imgs/3/e/3e07a9c3.gif)